
第29回全米サービス・ラーニング年次大会も最終日となりました。この日は参加希望者が2組に分かれ、ツイン・シティーズでのサービス活動を行います。

まずは全員集合。本日の内容について話があった後、1日活動組、半日活動組に分かれます。

ただし、1日活動組、半日活動組の中でも、いくつか活動内容が分かれているとのことです。
ちなみに、私は半日活動組。実は本学からはもう1人参加者がいて、そちらは前者に参加すると聞いていたので、かぶらないようにしたのです。

出発前にドラム演奏の披露。どういう理由なのか、ちゃんと分かってるわけではないのですが、参加者への敬意と景気付けみたいなもんでしょうか。
1日組が出発すると、半日組ではワークショップ(というか小グループでのディスカッション)と全体でのアイスブレイクを行います。詳しい内容は省きますが、ディスカッションでの話の中で、ある方が以前サービス・ラーニングのプログラムを運営していたのが無くなってしまい、それを復活させる手掛かりを得るために大会に参加した、と伺ったのが印象に残りました。この分野で先進的なはずのアメリカでも、上手くいかないことはあるんですよね。当たり前と言えばその通りなのですが、実際にお話を聞くと聞かないのでは、現実への理解の度合いは、まるで違います。

さて、事前学習も終わり、いよいよ活動場所に向かいます。活動場所は4ヶ所に分かれていて、それぞれバスが指定されています。

活動場所の違いは、事前に配られたリストバンドで判断します。私が貰ったのは赤色。読みにくくて申し訳ないのですが、バンドには大きく"Dare to Dream"(夢を見る勇気を持て、ぐらいかな)とあります。良い言葉です。

バスに乗る前、ランチボックスを貰いました。サンドイッチだそうですが、このサイズです。隣のコーラの缶と比べてみてください。

開けてみたところ、こんなんです。サンドイッチだけでも結構な大きさとして、リンゴがまるっぽなのも良いとして、ビスケットが巨大です。食後のデザートと言われても正直困惑するサイズです。あげくポテトチップってアータ。ランチでってアータ。

そんなチョコチップクッキーなんですが、裏面を見ると370kcalと書いてました。そらアメリカ人、こればぁ食べとったら太るわ……と思っていたら、全部食べてない人も少なからずいました。
ちなみに、私はサンドイッチとリンゴだけ食べて、残りは夜食以降に回しました。ドリンクもいくつか種類があって、アメリカっぽさを考えて日本では見かけないコーラを選んでみたのですが、人工甘味料・人工甘味料・アンド・人工甘味料、いろいろ通り越して笑いそうになりました。

バスで20分程、本日の活動場所に到着しました。ここは地元の方々から寄せられた寄付品を販売するリサイクルショップです。

店舗は障がいのある人を雇用するとともに、ボランティアスタッフの手もつつ運営しているとのこと。バックヤードにはボランティアスタッフのための掲示板があります。

ボランティアスタッフへの謝意を示す飾りつけ。こういうのは日本でも見習いたいものです。

私が担当したのは古着の整理。地域の方々から集められた古着を袋詰めして、コンテナにまとめ、搬入口に停まっているトラックに積み込んでいく作業です。

服を詰める袋はこんな感じで、再利用のポリ袋やレジ袋です。なので、内容量は大きく変動します。ただ、リサイクルのためにわざわざ新しいポリ袋を消費するよりは合理的、とも言えます。

集まってくる寄付品は多種多様。電化製品や家具、中には絵画もあります。それをスタッフがひとつひとつチェックしています。

バックヤードを出たところに、寄付品の提供場所がありました。地域の人々が車で乗り付けてきて、ここで寄付品を降ろしていきます。その際はベルを鳴らしてスタッフに知らせることになっているそうで、私の活動中も数分おきばぁでベルが鳴るのが聴こえました。

外には寄付に関する注意書が大きく出ています。外に放置しないこと、修理が必要なものや使用不可能なものはノーサンキュー、隣の青い案内標識には、受付時間外の寄付お断りとも書かれています。寄付してやるんだから何でも拝んで受け取れ、という感覚の持ち主には、そのままお帰りいただくことになるわけです。こうでなきゃね。

空き時間があったので、店内を観に行ってみました。この辺りは食器売り場ですが、他にも洋服や古本、中古CD、雑貨といろいろあります。

こちらは雑貨コーナー。よくみるとウサギのおもちゃやぬいぐるみがあります。やはりイースター前ということで、別の場所には特設コーナーっぽいのもありました。
そんな店内を一通り歩いて、気に入ったものをいくつか購入。申し出ればお釣りを店に寄付することもできるそうで、置いていくことにしました。と言っても、数十セントに過ぎませんが。

一通り活動を終えて、大会会場に戻って来ました。見ると、周囲にいくつも小さいボードが置かれています。何か見たことあるな、と思ったら、国連による持続可能な開発目標(SDGs)の17のゴールです。SDGs、ピンとこない方はこちらをどうぞ。
■ SDGs(持続可能な開発目標) 持続可能な開発のための2030アジェンダ | 外務省
ここからは活動を踏まえたリフレクション(省察)。ここでの課題は2つあり、まずは当日の活動を踏まえ、何を行ったのか、何が分かったのか、世界への観方がどう変わったのかを考えて、他の参加者とシェアします(とカッコつけてみましたが、要は誰か相手を見つけてお互い話し合う、ってことです)。3つ目の質問は難しいなぁと思ったところ、他の人も同様だったようで、困ったなぁと話し合うだけになってしまったのはナイショです。
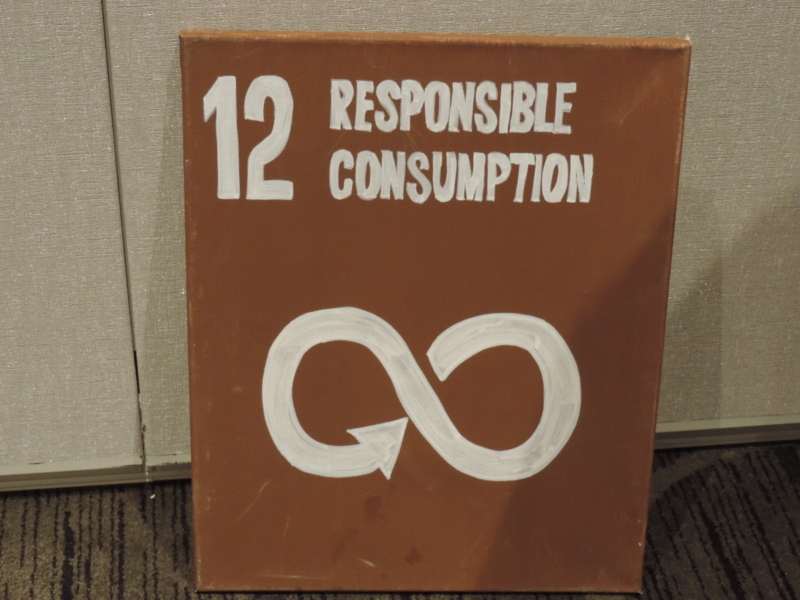
2つ目の課題は、SDGsのゴールの中で、自身が関心があるものを選び、同じゴールを選んだ人どうしで意見をシェアするというものです。
私が選んだのは12番目のゴール、日本語では「つくる責任 つかう責任」となってます。かなりの意訳ですが、こういうものはキャッチーさがカギですし、良いんじゃないかと。
近代社会に生きている限り、誰もが消費者になっているわけです。ということは、消費のあり方を変えることは、誰でもすぐに取り組めるゴールなはずだ、というのが私の考えです。第12ゴールに集まった人とこんな話をしながら、さらに話題は食品廃棄物をやフードバンクの問題に移っていきました。
最後は、各ゴールから代表者が出て、それぞれで話し合った内容をシェアして、リフレクションは終了。3日間続いた会議も、これにてお開きです。
それにしても、サービス活動がSDGsに結び付く辺りは興味深いことで、表現が拙くなってしまうのをお許しいただきたいのですが、アメリカのサービス・ラーニングが目指すものの深遠さというのを見せつけられた気がします。
この点をどう捉えるべきか、意見は分かれるでしょう。率直に言えば、私個人はこのようなあり方に非常に親近感を覚えます。ただそうでないにしても、「本場」のサービス・ラーニングの背景を理解することぐらいは、サービス・ラーニング自体の理解のためにも必要だろうとは言えそうな気がします。ですが、同時に、「サービス=社会奉仕」という通念を打破しない限り、このような理解は不可能だろうとも思っています。
他にもいろいろ考えたことはあるのですが、情けないことに、まだまとまってません(汗)。この3日間で圧倒的な情報や概念や思想を浴びた気がするもので、まだ消化不良気味なのです。いずれ何かの形でまとめて発信できれば良いのですが、いつになるやら……
←[前のエントリ]